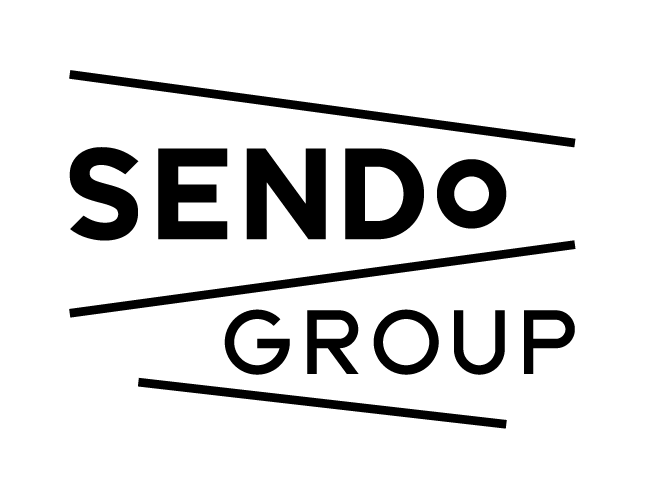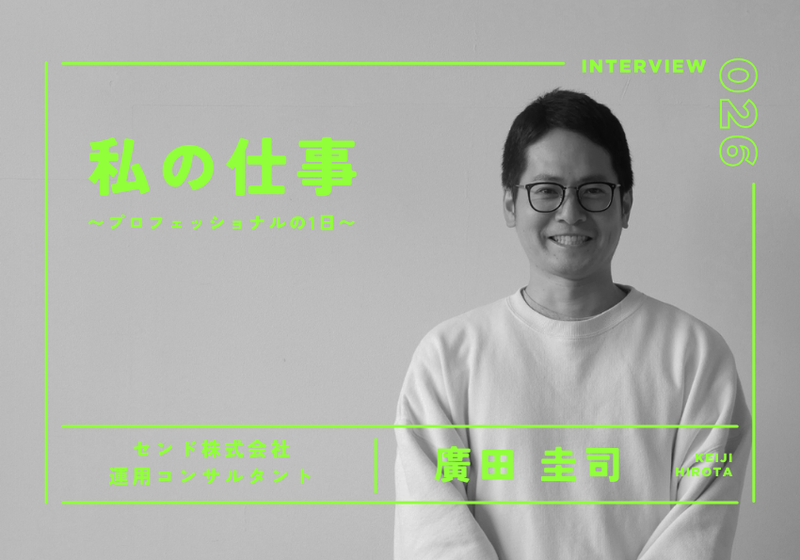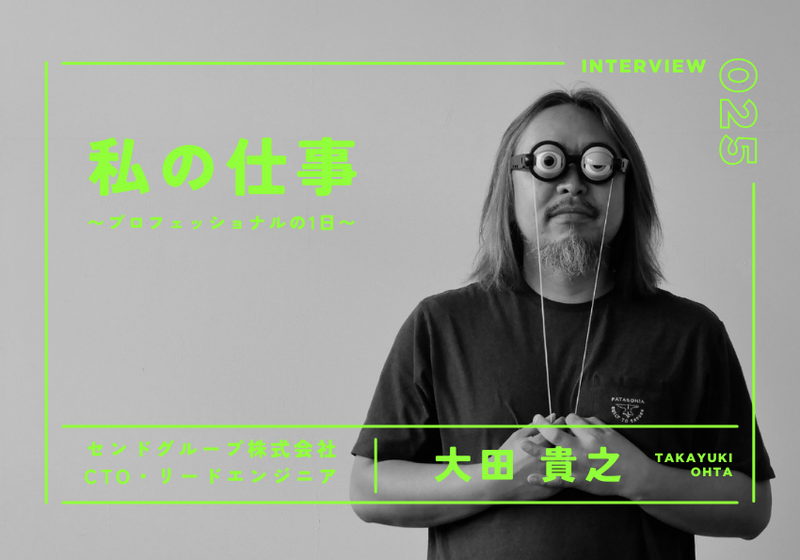Blog
最新情報をブログでお楽しみください
有給休暇はいつから?付与日数や期限、時間休など基本ルールを解説

こんにちは、つつみです。
センドグループのブログをご覧くださりありがとうございます。
最近勤怠チェック作業を引継ぐことになりまして、労務について知識を習得しているところです。
今日はその労務に関連する「有給休暇」についてお話したいと思います。
聞きなれた言葉ですが、その仕組みやルールを正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。「いつから使えるの?」「理由は書かないといけない?」「時間単位で取れるの?」など、身近なのに“あやふや”な点が多いのが有給休暇です。
今回は、有給休暇の基本をおさらいしながら、センドグループでの休暇制度についてもご紹介します。
まず知っておきたい「有給休暇の基本」
付与日と日数の仕組み
有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法で定められた働く人の権利です。
入社から6か月が経過し、全労働日の8割以上を勤務していれば、 10日間の有給休暇が付与されます。その後は勤続年数に応じて日数が増え、 最大で年間20日まで取得できるようになります。
パート・時短勤務の方も、勤務日数に応じて付与されます。
例)2025年4月1日に入社した社員
入社から6か月後・・・2025年10月1日に 【10日】 付与される
入社から1年6か月後・・・2026年10月1日に 【11日】 付与される
ちなみに、入社して6か月のあいだに体調不良などで欠勤が多く、出勤率が8割未満だった場合はその時点では有給休暇は発生しません。その後6か月(入社後1年)働き、出勤率が80%を超えていたら付与されます。
有効期限と注意点
付与された有給休暇には2年間の有効期限があります。
例えば、2023年11月に付与された10日は、2025年10月までに使わなければ失効します。翌年度に繰り越せるのは1年分までなので、計画的&定期的に取得してリフレッシュしましょう。
また企業によっては「積立有給休暇」や「保存休暇」という期限切れで消えるはずの有給を積み立てておける制度を導入している場合があります。
主に長期入院・けが・介護・看護など、やむを得ない事情で仕事を休むときに使える特別な休暇です。センドグループでは導入されていませんが、社員が安心して働ける環境をつくる取り組みとして導入が広がっています。
年5日の取得義務って?
2019年の法改正により、企業には「年10日以上の有給休暇が付与される労働者」に年5日以上の有給休暇を取得させる義務があります。
これは「会社が管理責任を持って、必ず5日は休ませる」ことを意味します。弊社ではキンコンという勤怠ツールを使用しており、対象者へアラートが送られるようになっています。
年5日は有休を取得する義務があるので、あまり有休を取得していない方はぜひお休みの計画を立ててみて下さい。
休暇の理由は書かなくてもOK
有給休暇は「法律で認められた権利」なので、取得理由を伝える必要はありません。
「私用」「プライベートの用事」など一言で済ませても問題ありません。
▼参考:厚生労働省
年次有給休暇取得促進特設サイト
年次有給休暇制度について
センドグループでの有給休暇
取得しやすい環境
・令和5年の年次有給休暇の取得率は65.3%
・30~99人規模の会社では63.7%
※労働条件分科会「2023年度 年度評価参考資料集」より
センドグループの令和5年の取得率は71.4%と、他社と比べて有給休暇を取得しやすい環境のようです。 連休と組み合わせて旅行に行くメンバーも多く、お土産菓子が集まる楽しみもあります。
「時間休」を導入
「時間休」とは、時間単位で有給休暇を取得できる制度です。
「午前休・午後休」の半休は多くの会社にありますが、「時間休」はすべての企業に導入されているわけではありません。
労使協定を結ぶことで導入でき、柔軟な働き方を支援するために採用する企業が増えています。
センドグループでも時間休制度が導入されています。時間休を取得して子どもの授業参観へ行ったり、通院してから出社したり、昼休みと合わせて役所や銀行に行くことができたりと、柔軟な働き方が可能となりました。
ちなみにこの「時間休」は年5日の有給休暇の取得義務の日数にはカウントされないため、取得時間に上限が設定されています。
有給休暇以外の休暇制度も紹介
センドグループでは、有給休暇のほかにもさまざまな休暇制度を整えています。
特別休暇
結婚・出産・忌引など、人生の節目をサポートする休暇です。
社員が安心して生活のイベントを迎えられるよう、柔軟に取得できる仕組みが整っています。
子の看護等休暇
子育てをしながら働く社員のために、法定の休暇制度ももちろん対応。
センドグループでは従業員の生活も大切に考え、子育てと仕事を無理なく両立できるよう「子の看護等休暇」を有給で取得することができます。
まとめ
有給休暇は会社からもらうものではなく「自分が持っている権利」です。
また、時間休や子の看護等休暇の有給取得など、会社によって働く環境を考えて整備している制度もあります。
今回の記事で「そうなんだ!」ということが一つでもあったら幸いです。
読んでいただきありがとうございました。