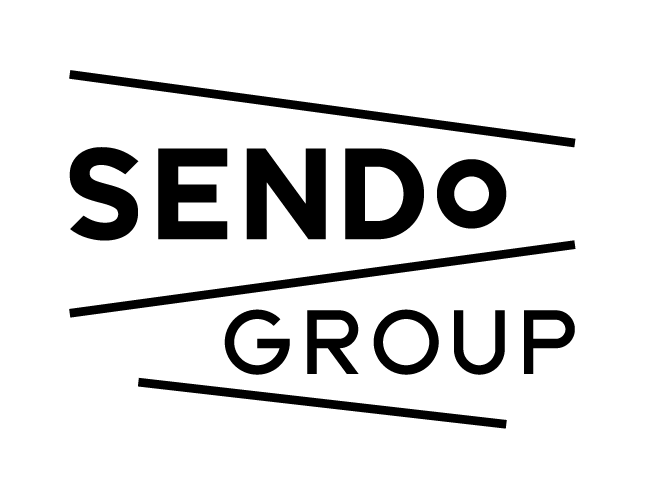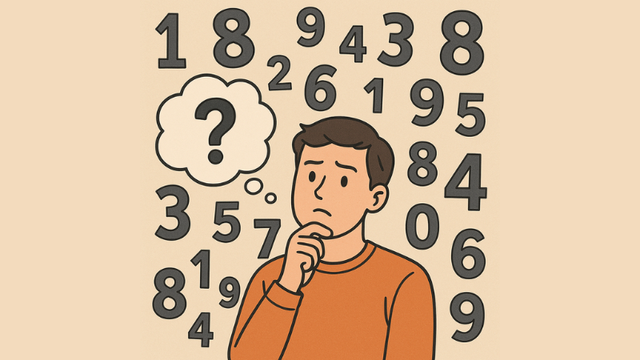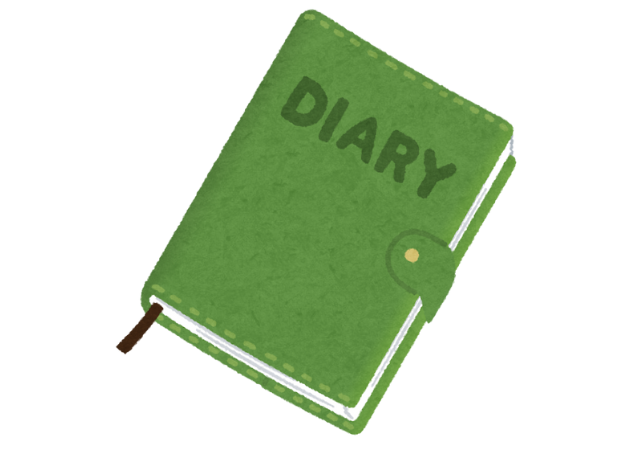なお、開発G(G=グループ)では「数字で語れる文化に」を実現するためにいろんなカットで数字を扱う基盤を構築中です。
まずは経営視点から。
企業の経営における数字を見るポイントは?
▼AIの回答ここから▼
経営を数字で見るポイントは、大きく分けて以下の5つの視点で整理できます👇 とのことです。
収益性(どれだけ儲かっているか)
経営で最も基本的な問いは「儲かっているのか?」です。
売上の大きさではなく、利益構造の質を見ることが重要です。
| 指標 | 意味 | 経営での読み方 |
|---|---|---|
| 売上高(Revenue) | 活動量・市場シェアの大きさ | 「市場でどれだけ取引しているか」 |
| 売上総利益(粗利) | 売上 − 原価 | 「本業の採算力」 |
| 営業利益 / 営業利益率 | 売上 − 原価 − 販管費 | 「事業運営の効率性」 |
| 経常利益 / 当期純利益 | 本業+金融+特別要因を含む最終利益 | 「企業全体の収益力」 |
| ROE / ROA | 自己資本・総資産に対する利益率 | 「資本をどれだけ効率的に回しているか」 |
ポイント
-
「売上が増えている=良い」とは限らない。
粗利率や営業利益率が悪化していれば危険信号。 - 収益構造の健全性は「粗利率 × 販管費率 × 営業利益率」の推移で見る。
安全性(潰れない体質か)
利益が出ていても、キャッシュが回らなければ会社は倒れます。
資金繰りと財務の安定性を数字で追うことが重要です。
| 指標 | 意味 | 経営での読み方 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 総資産に対する自己資本の割合 | 「財務の安定度(40%以上が理想)」 |
| 流動比率 / 当座比率 | 短期支払能力 | 「短期的な資金余力」 |
| 営業キャッシュフロー | 本業で生んだ現金 | 「事業が現金を生み出しているか」 |
| 借入金依存度 | 負債総額 / 総資産 | 「過度なレバレッジになっていないか」 |
ポイント
- 「黒字倒産」を防ぐには、利益よりもキャッシュフローを重視する。
- 粗利や売上より、「現金が入るタイミング」を把握する。
成長性(将来伸びるか)
経営のゴールは、持続的な成長。
過去→現在→未来の「トレンド変化」を数値で把握します。
| 指標 | 意味 | 経営での読み方 |
|---|---|---|
| 売上成長率 | 前期比売上増加率 | 「事業拡大のスピード」 |
| 営業利益成長率 | 利益の伸び率 | 「効率的に成長しているか」 |
| 顧客数 / 単価 / 継続率 | 売上の分解要素 | 「どの要素が伸びているか」 |
| LTV / CAC | 顧客生涯価値と獲得コスト | 「長期的に利益が出るか」 |
ポイント
- 成長性は絶対値よりも“推移”が重要。
- 新規事業や顧客単価の伸び率に注目。
効率性(どれだけムダなく回しているか)
限られたリソースでどれだけ成果を出しているか。
経営者は「費用対効果」を常に数字で測ります。
| 指標 | 意味 | 経営での読み方 |
|---|---|---|
| 労働分配率 | 人件費 ÷ 付加価値 | 「人件費が利益を圧迫していないか」 |
| 一人当たり売上 / 利益 | 生産性の指標 | 「社員の稼ぐ力」 |
| 固定費比率 | 売上に占める固定費の割合 | 「損益分岐点の高さ」 |
| 在庫回転率 / 売掛金回収率 | 資金効率 | 「資金をどれだけ回しているか」 |
ポイント
- 「売上が増えても人員が増えすぎたら非効率」
- 「どのコストが利益を生まないか」を数字で特定する。
事業ポートフォリオ(バランス)
複数事業を持つ場合は、どの事業が収益を支え、どれが未来を作っているかを把握します。
| 指標 | 意味 | 経営での読み方 |
|---|---|---|
| 事業別売上・利益構成比 | 各事業の収益貢献度 | 「主力と育成のバランス」 |
| チャネル別ROI / ROAS | 投資対効果 | 「投資配分の最適化」 |
| 事業別成長率 | 各領域の伸び | 「どの柱を育てるか」 |
ポイント
- 「今儲かっている事業」と「将来伸びる事業」は別。
- 経営は常に「再配分の判断」。
補助指標(経営の健全性・組織面)
| 指標 | 意味 | 経営での読み方 |
|---|---|---|
| 離職率 / 採用充足率 | 組織の安定性 | 「人材が定着しているか」 |
| 社員満足度(eNPS) | 内部エンゲージメント | 「持続的なパフォーマンスの源泉」 |
| 顧客満足度(NPS) | 外部の信頼 | 「ブランドとリピート率の先行指標」 |
経営数字の見方まとめ
| 視点 | 主な指標 | 経営での意味 |
|---|---|---|
| 収益性 | 売上・利益・ROE | 儲けの構造 |
| 安全性 | 自己資本比率・CF | 倒れにくさ |
| 成長性 | 売上成長率・LTV/CAC | 将来性 |
| 効率性 | 一人当たり利益・固定費比率 | 生産性 |
| ポートフォリオ | 事業別構成比 | リスク分散・資源配分 |
▲AIの回答ここまで▲
なるほどなるほど。続いて開発における数字を聞いてみます。
開発組織における数字を見るポイントは?
▼AIの回答ここから▼
「開発組織における数字を見る」というのは、
単にコードやリリース数を数えることではなく、
“開発チームがどれだけ価値を継続的に生み出せているか”
を定量的に理解することを意味します。
経営や事業の数字と違って、開発組織の数字は「成果(アウトカム)」と「プロセス(アウトプット)」の両面を捉える必要があります。
以下の5つの視点で整理してみましょう👇
生産性(Delivery / Throughput)
開発チームがどれだけ効率的に成果物を届けているか。
| 指標 | 内容 | 経営・マネジメントでの意味 |
|---|---|---|
| リードタイム(Lead Time) | 要件〜リリースまでの平均日数 | フロー効率の可視化(短いほど俊敏) |
| サイクルタイム(Cycle Time) | 開発着手〜レビュー完了まで | チームの開発スピード |
| デプロイ頻度(Deployment Frequency) | 本番リリース回数 | 継続的デリバリーの成熟度 |
| 完了ストーリー数 / ベロシティ | スプリントごとの完了量 | 開発ペースの安定度 |
| WIP(Work in Progress)数 | 同時進行中のタスク数 | ボトルネック・マルチタスク検知 |
ポイント
- 「量」よりも「安定性」を見る(波が大きいチームは不安定)
- ベロシティを評価指標にせず、改善指標として使うのが健全。
品質(Quality)
開発成果の安定性と保守性。
数字で品質を管理できると、後戻りコストを減らせます。
| 指標 | 内容 | 意味 |
|---|---|---|
| バグ報告数 / 修正率 | リリース後の不具合と対応速度 | 品質と対応力 |
| リグレッション率 | 修正後に再発した不具合の割合 | テストと設計品質 |
| テストカバレッジ | 自動テストがカバーするコード率 | 開発プロセスの信頼性 |
| コードレビュー時間 | PR作成〜マージまでの平均時間 | チーム協調と品質確保のバランス |
| エラー率 / 障害発生率 | 本番エラー件数 | 運用品質・安定稼働性 |
ポイント
- バグ件数は「多い/少ない」よりもトレンドで改善傾向を見る。
- コードの静的解析やSonarQubeなどで技術的負債を定量化。
効率性(Efficiency)
チームリソースや開発プロセスをどれだけ効率的に使えているか。
| 指標 | 内容 | 意味 |
|---|---|---|
| 1人あたりチケット完了数 / 工数 | メンバーの生産効率 | 成果と負荷のバランス |
| レビュー滞留時間 | レビュー待ちで止まっている時間 | ボトルネック可視化 |
| 自動化率 | CI/CD、自動テスト、デプロイ自動化 | 効率的なオペレーション度 |
| 環境セットアップ時間 | 新人・PJ立ち上げ時間 | チームのスケーラビリティ |
ポイント
- 「努力量」ではなく仕組み化率(自動化・再利用)を見る。
- 人依存が減っているかが健全な組織のサイン。
チーム健全性(Team Health)
生産性や品質の基盤となる「人と組織の状態」。
| 指標 | 内容 | 意味 |
|---|---|---|
| バーンダウンチャート / スプリント完了率 | 計画 vs 実績 | チームの見積精度と安定度 |
| 稼働率 / 残業時間 | チーム負荷 | サステナビリティ |
| eNPS(従業員満足度) | チームモラル | 離職・燃え尽きリスクの早期検知 |
| メンバー継続率 | 離職・配置転換率 | 組織安定性 |
| 学習・改善回数 | レトロスペクティブでの改善項目数 | 継続的改善文化の成熟度 |
ポイント
- 健全性は「数字 + 会話」で確認(定量だけでは測れない)
- 短期成果より長期の持続性を重視する。
ビジネス貢献度(Impact)
開発がどれだけ事業・顧客価値に貢献しているか。
ここを数字で語れると「経営と開発」がつながります。
| 指標 | 内容 | 意味 |
|---|---|---|
| 機能利用率 / アクティブ率 | リリース機能の利用状況 | 本当に価値を生んでいるか |
| リリース後のCV / 売上増加率 | 機能が事業指標へ与えた影響 | アウトカム指標 |
| 障害対応時間 / MTTR | 復旧スピード | 信頼性と顧客満足度 |
| 技術負債返済率 | リファクタリング・改善投資率 | 長期的な健全性 |
ポイント
- 「何を作ったか」より「どれだけ価値を生んだか」を見る。
- KPIを事業KGIに連動させる(例:リリース機能 → CV率 +5%)。
▲AIの回答ここまで▲
なるほどなるほど。昨今では、ROI(投資対効果)を見よ。という記事をよく目にします。
AIに聞くと、
単に「開発した/リリースした」というアウトプットではなく、「どれだけ価値を生んだか/生み続けうるか」を定量的に把握し、経営・事業・開発現場の三者をつなぐ非常に重要な視点です
とのことです。最後のビジネス貢献度があてはまりそうです。更に問うてみます。
ビジネス貢献度が該当する?
▼AIの回答ここから▼
はい、まさにその通りです。
開発組織における ROI(投資対効果) の考え方は、あなたが先に挙げていた
「ビジネス貢献度(Business Impact)」という視点と ほぼ一致します。
違いを整理すると、こうなります👇
| 観点 | ROI(投資対効果) | ビジネス貢献度(Business Impact) |
|---|---|---|
| 定義 | 投資に対して得られた成果(Return)を定量的に評価する | 開発活動が事業・顧客価値にどれだけ寄与したかを測る |
| 数式的アプローチ | ROI = (利益や価値の増加 − 投資コスト) ÷ 投資コスト | 売上・効率・顧客満足などの成果を多面的に評価 |
| 焦点 | 「お金の観点」から開発の価値を測る | 「事業価値の観点」から開発の意味を測る |
| 時間軸 | 比較的短〜中期で成果を見る(投資回収) | 中長期での事業貢献や顧客価値創出 |
| 対象 | プロジェクト単位・施策単位の評価 | チーム・組織・プロダクト全体の評価 |
| 経営的意義 | リソース配分判断の根拠 | 経営戦略との整合性の確認 |
| 例 | 「自動化ツール開発コスト500万円で、年間運用コストを1,000万円削減 → ROI=100%」 | 「新ダッシュボード導入で顧客リテンション+5%、顧客満足度改善」 |
開発組織がROIを語るとき、それは単に「費用対効果」だけではなく、
“自分たちの開発がどれだけビジネスの成果を生んでいるか” を説明すること。
この「成果部分」がまさに ビジネス貢献度 です。
ビジネス貢献度(=ROIのリターン側)を構成する主な要素
| カテゴリ | 指標例 | ROI換算の考え方 |
|---|---|---|
| 売上向上 | CVR改善、LTV増加、アップセル率 | 収益増加分をリターンとして算入 |
| コスト削減 | 工数削減、自動化、障害削減 | 削減された人件費・機会損失を金額換算 |
| 顧客価値向上 | NPS向上、離脱率低下 | 顧客維持によるLTV増を見積もる |
| 品質・安定性 | MTTR短縮、障害減少 | システム停止による損失回避をリターン化 |
| 市場・ブランド効果 | 指名検索数、紹介率 | 将来顧客獲得コスト低下の要因に換算 |
▲AIの回答ここまで▲
今後はこれらの要素も考慮して、計画や目標設定の数字の参考にしたいと思います。
まだまだ続きます。
ここまで数字の話をしてきましたが、2025年7月3日に開発生産性カンファレンスが開催されました。
そこで25年ぶりに来日したケント・ベックという著名な人が「グッドハートの法則はもっと悲観的に捉えるべきだった」と話してます。
https://dev-productivity-con.findy-code.io/2025
グッドハートの法則
「指標が目標になると、その指標は良い指標でなくなる」
When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.
— チャールズ・グッドハート(Charles Goodhart, 1975)
意味(簡潔に言うと)
本来は「成果を測るための指標」が、
評価・報酬・目標の対象になった瞬間に、歪みや不正確さが生まれるという警告です。
つまり:
「数字を追うこと」が目的になると、
「数字が示す本来の意味」が失われてしまう。
起源と背景
- イギリスの経済学者 チャールズ・グッドハート が1975年に発表。
-
当時、英国政府が「経済のマネタリズム政策(通貨供給量管理)」を指標で管理していたが、
その指標が政策目標になると市場参加者がそれを操作し、意味を失ったことがきっかけ。 - その後、社会科学・経営・教育・IT開発などあらゆる分野で引用されるようになりました。
とのことです。例を上げてもらいましょう。
| 指標 | 意図 | 歪んだ行動 |
|---|---|---|
| 契約件数の増加 | 売上拡大 | 単価を下げて契約数を稼ぐ/不適切な顧客にも販売 |
| 問い合わせ件数 | リード獲得の活性化 | ノイズ的なリードを増やして数字だけ上げる |
| NPS(顧客満足度) | 顧客体験の改善 | “高評価お願いキャンペーン”を行い、数値操作 |
| 社員稼働率 | 生産性向上 | 非効率な仕事でも“忙しいふり”をして稼働率を高く見せる |
| 在庫回転率 | キャッシュ効率改善 | 不要な値下げで在庫処分、利益率を悪化させる |
| 逮捕件数 | 治安改善 | 軽微な違反を過剰に取り締まる/重大事件の捜査を後回し |
| 病院の平均待ち時間 | 医療サービスの効率化 | 重症患者を後回しにして平均時間を下げる |
| 公共事業の完了件数 | 行政効率 | 短期で終わる小規模工事ばかり選ぶ |
| 失業率の低下 | 雇用促進 | 雇用統計の定義変更や短期雇用の増加で“数字上の改善” |
| テストの平均点上昇 | 学力向上 | 試験対策に偏る・暗記中心になる |
| 進学率 | 教育水準向上 | 無理な進学指導・統計操作 |
| 欠席率の低下 | 生徒の生活改善 | 登校だけ強制して内面的な支援をしない |
KPIをインセンティブと直結させると、「数字のための行動」が発生し、数字は“目的の代理”であり、“目的そのもの”ではない。とのことです。
対策まとめ
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| 数字が目的化している | 「なぜその指標を追うのか」を常に共有 |
| 単一指標で判断 | 複数KPIでバランス評価(速度×品質など) |
| 定量だけで評価 | 定性データ(顧客の声・チームの声)も併用 |
| 報酬が数字に直結 | 数字以外の行動・学習を評価項目に含める |
ちなみに、上記のカンファレンスでケント・ベック氏は、Impactが重要と言ってます。
Effort(工数) → Output(生成物) → Outcome(成果) → Impact(影響)(ビジネス上の利益(ROI)など)
投資家も投資に対するリターン(ROI)を見ます。我々もその視点を持つべきですと。
Impactの測定は プログラマー一人当たりの利益など直接測定は難しいですが、これが究極の目標とのこと。
AI時代については、AIによって増えたコードの量(Output)ではなく、若手の学び(Outcome) こそが長期的に見て価値を生むので重要とのこと。
Findyさんのブログで日本語訳を記事にしてくれてますので興味がある方はどうぞ。
https://tech.findy.co.jp/entry/2025/10/20/070000
https://tech.findy.co.jp/entry/2025/10/21/070000
終わり
他にも数字関連でいうと推測するな、計測せよという有名な言葉もありますが、ROIを意識した指標と目的を心がけたいと思います。